HOME>魚介類の種類と栄養成分>かつお
かつおの栄養成分と食べ方のアドバイス!
カツオという魚は赤身の魚で、春と秋に旬があります。
春のカツオは初鰹とも呼ばれ初夏の味として古くから多くの人に親しまれています。
一方秋にとれるカツオは戻り鰹と呼ばれ、あっさりした味わいの初鰹に比べると、たっぷり脂がのっているのが特徴です。
鰹の食べ方としては、タタキと呼ばれる調理法が一般的ですが、にんにくと合わせたステーキなども親しまれているようです。
鰹を選ぶときのポイントは、身の色が鮮やかで血合いがはっきりしているものが良いでしょう。
栄養価としては脂がのっている戻り鰹のほうが上ですが、どちらにも共通して言えることは良質のタンパク質が100g中25gも含まれている点です。
さらに、鉄分も1,9mg程度含まれておりますし、ビタミン類ではB群やD、ナイアシンの多さが目立ちます。
赤みということもあるのか、特に血合いの部分にはビタミンやミネラルが豊富に含まれています。
※μg(マイクログラム)は1gの10万分の一/mgは1gの千分の一
スポンサードリンク
|
◆ワンポイントアドバイス
・食べると良い時期(旬)
初夏〜秋
・理想的な保存期間の目安(賞味期限)
冷蔵庫で1〜2日程度 |
 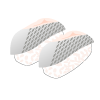  |
かつおの効能とは!
鰹に含まれるビタミンB群には、赤血球の生成を促進するB12が100g中8,4μgと豊富に含まれています。この効能としては貧血の予防に効果を発揮します。
DHAも目の裏側の脂肪に多く含まれています。
このDHAは、脳細胞を活性化しますので、学習能力を高める効果があると言われますし、コレステロールを減少させる効果や血管をしなやかにもします。
さらに、含まれているナイアシンにも脳と神経系の健康を保つ働きがあります。
結論としては、カツオは血液をサラサラにしたり血管も若くして、なおかつ脳の働きも活発にする魚です。 |
スポンサードリンク
|