HOME>魚介類の種類と栄養成分>鯛
鯛の栄養成分と食べ方のアドバイス!
たい(鯛)にはマダイやチダイ、レンコダイ、黒鯛、ヘダイ、など多くの種類がありますが、たい(鯛)といえば一般的にマダイ(真鯛)を指し、ほとんどが養殖によるものです。。
ちなみに、最も真鯛に似ているのはチダイ(ハナダイ)と呼ばれ、素人目にはほとんど見分けは付きません。そのため、時々このチダイ(ハナダイ)がスーパーでタイとか、時には真鯛とか書かれて売られているのをが見られます。・・・これも一種の食品偽装と言うのでしょうか?
たい(鯛)は、高たんぱくで低脂肪の代表的な白身の魚です。ただ養殖のものは天然に比べどうしても脂質が多くなってしまい、その量100g中約5gに対して養殖は約11gと2倍程度になります。
他の栄養素では、ビタミンB1やEの含有量が多いのは特徴です。
食べ方としては、刺身や塩焼き、煮付け、混ぜご飯、吸い物、洋食など、タンパクで癖がないせいか多くの料理に使われます。
選び方は、目が澄んでいて色が鮮やかのものが良いでしょう。
※μg(マイクログラム)は1gの10万分の一/mgは1gの千分の一
スポンサードリンク
|
◆ワンポイントアドバイス
・食べると良い時期(旬)
春
・理想的な保存期間の目安(賞味期限)
冷蔵庫で2〜3日程度 |
 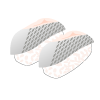  |
鯛の効能とは!
たい(鯛)に多く含まれているタンパク質は良質のタンパク質です。
良質のタンパク質とは、体のタンパク質のアミノ酸構成に近いものほど、体のタンパク質を合成する上で良質とされます。
たい(鯛)の皮に多く含まれるビタミンB2には、皮膚や目、口の中の粘膜を健康に保つ働きがあります。
さらに、ビタミンEには抗酸化作用や血行を促進する効果がありますので、細胞を若返らせことが可能です。 |
|